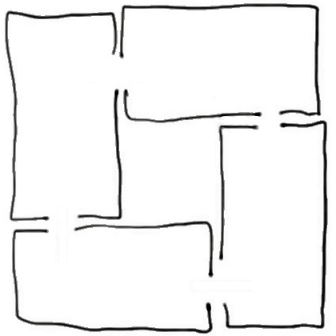対談
正岡子規、躍動する運動神経
──「別に一体」に向けて
岡井隆
平出隆
(注:この稿は『正岡子規──俳句・短歌革新の日本近代』(「KAWADE 道の手帖」、2010年)のために行なわれた対談の文字起し稿(平出隆所蔵のWordファイル)から再現されたもので、最終掲載稿とのあいだに若干の異同がある。対談は2010年8月11日。)
左利きの強打者?
岡井 大体不思議なんですよね、平出さんがなぜ正岡子規か。伊良子清白なんかとつながっているんですか、平出さんの中では。
平出 最初は野球なんですよ(笑)。
岡井 あ、野球ね、そうか。
平出 『ベースボールの詩学』という本を一九八九年に出したんですが、そのときにアメリカにおける野球はアメリカに起源があるとは神話に過ぎない、という問題を中心にしました。ちょうど百年前に、つまり一八八八年から八九年にかけて、スポルディングが野球を興行しながら世界一周をする。その中で全体はアメリカの野球とホイットマンなどの思想とか野球のエジプト起源説とかを絡めて進むんですが、その九章の構成の中に日本における詩と野球との関係というのを出したかった。そのスポルディングの遠征の時期は、ちょうど子規が一所懸命、ベースボールを実践していた時期なんです。スポルディング一行は日本には立ち寄らなかった。しかし、その時期に、正岡子規がベースボールの本質を直観で、あるいは素手でつかまえていた。そこで、プレイヤーとしての子規を調べていって、そのまま「短詩型プレイヤー」として、一章を子規にあてたというところで……まあ本当に野球から入って行ったんです(笑)。
岡井 でもそういう意味では不思議ですね、子規っていうのは。司馬さんが書かれて、テレビの「坂の上の雲」で最初に松山の練習場か何かで、子規が帰郷するたびに高浜虚子か何かが相手しながら野球やりましたよね、ああいうところが出てきたりするんだけど、子規はご承知のように病身で弱いし、それからお母さんに言わせると、てんで運動神経はだめで、もうあらゆることがど下手でだめなんだ、っていうことをあのお母さんが独特の口調でね。亡くなってからですかね、あれは。回想録で言ってましたけど。この間子規の病気のことを書いた本を読んでたら、多少同情的に見ていたのは、彼みたいな体型の人っていうのは、わりとスポーツにはいいんじゃないかなって思っていたんですけど、二十歳で兵隊検査を受けますね、当時の平均身長は一五五センチぐらいですね。彼は一五六位で、夏目漱石が一五四だったかな、写真を見ていると、森鴎外なんて、外国人の横っちょに並んでいるせいか知らないけど、本当に何というか矮躯短身っていうふうに見えるんだけど、全体のプロポーションはいいんですよね。子規もそう。平均体重は五二キロか三キロかな。つまりあの頃の日本人の中では彼は標準よりは大きい方で、「そうか、それじゃあこれで結構やったんだな」と思ったんですけど、あのベースボールの歌はともかくとして、彼はやったんですか。
平出 ええ、かなりやったんですね。それでスコアが残っていますし、実際に、球遊びに明け暮れた時期があったんですね。
岡井 でもそう上手じゃないでしょう。
平出 強打者だったという説もないわけではないんです。キャッチャーだったらしいし、左利きだったとかっていう説もありますね。
岡井 左利きかな、彼は。
平出 その説もちょっと怪しいんですけど、ただ身体検査をして、昔の身体検査って上腕と下腕の周りとかずいぶん変なところをかなり細かく測っていて、それも頻繁に測っていて、それを彼は記録しているんです。それで野球をやっている時期に左腕がだんだん太くなっているんですよ(笑)。だからどうもやっぱり左利きだったのかなっていう気もする。ただ喀血の時期に重なりますから、にわかに健康を崩していくような時期なんです。
岡井 十五とか十八とか、あの辺で何回もやっていますよね。
平出 もう少しあとかな。明治二十一年に吐血、二十二年に喀血ですから。それでも野球をやるんだけれど、ボールとバットがなかなか出合わないっていう日が来まして、それで青ざめた、血の気の引いた顔だったらしいんです。その明治二十四年の球遊びでの様子を、碧梧桐が文章にしています。その辺からはっきり健康を崩していくんですね。
岡井 普通結核の人っていうのは、まあ僕はたくさん見たからあれだけど、大体顔面が紅潮している人なんか一人もいなくて、もうみんな青白いんですよ。全体にそういう人が多かったですね。本当は喀血というのは知らない間に出てくるんだけど、やっぱりそこそこ大量だと、明らかに身体の中のヘモグロビンが出て行っちゃいますから当然青ざめるんですよね。だから子規も書いているように、肉体的影響も大きいけれど、あれは心理的にいやなんだよね、こう見て赤いでしょう、「あっ、血吐いちゃった」っていうのがね。日清戦争に報道で行って帰りの船の中で吐きますよね。あの後すぐに須磨に引っ込んじゃってね。
平出 長かったですね、須磨の療養は。
俳句は百科全書的精神
岡井 この間亡くなられた玉城徹さんにも正岡子規についての本がありましたね。
平出 『子規——活動する精神』(北溟社)が二〇〇二年ですね。
岡井 『新潮』の子規没後一〇〇年特集(二〇〇二年一〇月)に玉城さんが「文士としての子規」というのを書いておられ、非常に面白く読みました。たとえば文士というような意識というのが子規の中に生じていたというのは非常に先見的であって当時誰も考えていなかった、というようなことを言ってらっしゃるんだけど、子規の両目は離れてて、だから右目と左目が別の方を向いていて、片方は非常に合理的なものを見ているんだけど、もう片方は非常にロマンチックなものを見ているって。本当ですか(笑)。
平出 そんなこと書いておられましたか(笑)。
岡井 書いてました。
平出 そうでしたっけ(笑)。
岡井 あれはたしかにちょっと離れていますね。自画像でも意識しているのかな。
平出 そうですね。香取秀真が作って持って来た子規の塑像には、子規自身が「額ガ平カ過ギル」とか批評を書き込んだんですね。目と目のあいだには「ツマリスギル」とありますね(笑)。
岡井 わりと文学の人って自分のことを意識してる。画家はよく自分の肖像画を描いたりするけど、子規ってわりと自分のことを見つめるタイプですね。
平出 意外に写真もたくさん残ってます。
岡井 あのお母さんの八重さんに言わせると無茶苦茶だけどね、「容貌が魁偉で醜さのかたまりである」とか散々言ってるけど、どうなんですかね。たしかにそう美男子とは私も思わないけれど、左右に分かれてるっていうことは、要するに片方は単なる感覚の解放、もう一つは精神の規律っていう意味で、いわば定型を選んだとかそういうところに関係しているのであって、まあ玉城さんの言うことは深遠だから(笑)普通のあれとは違うんだけど、容貌からそういう話をやっているところがちょっと面白かった。
平出 たしかに初めて会う人はちょっと驚いてしまう顔形だったかもしれないですね。それから驚いたあとにしげしげと見てしまう形だったかもしれないですね。
岡井 平出さんの今度の『鳥を探しに』という本を見ていると、博物学の宝庫みたいな本だけど、あなたも相当理系のことに詳しくて、しかも日本の学問は文と理を分けちゃっているのは間違っているんですけど、もういっぱいそういう方がいらっしゃいますね。正岡子規なんていうのも学校の成績はともかくとして、頭はかなり理系的ですよね。分類をやって、玉城さんがしきりに言うでしょう、その分類から知識の基礎に気づいていくと。そうすると江戸時代からずっとの俳句っていうのは、「この季語に関してはこう」、「この切り字に対してはこう」って、『俳諧大要』なんかを見てもそうだけど、もう理路整然としてるでしょう。あれは文化系というよりは理系のセンスじゃないですかね。玉城さんは啓蒙の精神だって言っているんだけど、啓蒙っていうのはつまりおまじないとか神話とかいうものを否定して合理性を言うんでしょう。だからずっと全部調べ上げてみたら、俳句っていうのは江戸時代から現代までの間にこういう構成をしているんだっていうことを自分で一生懸命分類したということはどうなんでしょう。
平出 『筆まかせ』みたいな、わりに若いときから書きつづけたものは、日記でもないですね、いろいろなものを手当たり次第に論じつつ整理していくっていう断章集ですけど。百科全書的な方法というか。
岡井 なるほど百科全書だね。百科全書的精神ですね、あの人は。
平出 だから俳句と言ったときに、もうすでに百科全書的な意味合いがそこに入っているんじゃないですかね。俳句の中に百科全書的な精神を見つけていた。
岡井 この間、子規の世界っていうのを角川書店から書けと言ってきて、このごろは私には長い文章を書かせないんですよ。それで巻頭のところでお飾りを三人ぐらい選んでね、二ページのものを書かせられるんですよ。それで腹が立ったから、「私は今の子規理解というか、そういうのは徹底的に論争してやりたいと思っているんだ」って言って、それで子規という人は、今の百科全書じゃないんですけれど、表現方法として同時に俳句を作って、それで大体俳人が短歌を作るっていうことがそもそも容易なことではないと私は思うんだけど、その上あの小まめなエッセイスタイルの、あれは僕は場合によると散文詩の一部分になり得る、『病牀六尺』にしたって『墨汁一滴』にしたってそう思うんですけど、そういったものと、それから最後に絵を描いたと。前からずっと絵は描いているけれど、それにしても最晩年のところで集中して絵を描いていると。そうすると、単純に言っても俳句作っている人が短歌を作るっていうことは容易でないってわかってきて、そこへ彼の最晩年っていうのは短歌はほとんどないですから、そうすると俳句とエッセイとそれから非常に重要な一つに明治三十五年あたりのスケッチ帳があるのではないかと。これは彼の自己表現で、そういうマルチの表現様式をとるっていうことは、自分でやってみればいいけれど大変なことで、しかも俳句だけに熱中していると短歌というのはなかなかできないし、その逆もそう。それでしかも最後の頃は、絵をあんなに熱心に、体力のない、もういつ死ぬかわからないという状況で描いている。だから総合芸術家なのだと思うんです。そういう総合芸術家というのはどういうものなのかっていうことを全然理解しなくて、俳人正岡子規、歌人正岡子規という、それであとは「楽しきエッセイを書いてくれた正岡子規」とか言って自分のお得意の部分だけで理解しているのは大間違いである、これらを総合して正岡子規というのは存在したという、こういう存在の仕方をした人という人が近代文学の一番初めのところにいたということをよくよく理解していただきたいと。正岡子規をカリスマだとか担ぎ上げる今の若者どもに向かって腹が立ったから言っているんだけど(笑)、どう思いますか。
平出 基本的に大賛成で、私もその線で『遊歩のグラフィスム』を書いたつもりなんです。
岡井 そうですね。
平出 そのときに、どういう言葉でとらえられるかというと、「詩人批評家」という言葉は一つありまして、鋭い形式意識が複数の領域間を渡るときに、領域の段差が批評的に見出される。「総合芸術」という言い方が最初からあるわけではないでしょう。彼の中で自分にぴったりくる学問を探していた若い時期がありますね。そういうときにさっきの「筆まかせ」という帖面に、次々とその渡り歩きを書くわけですけれど、それはあるときは随筆的で、あるときは批評的で、またあるときは哲学的ですね。哲学の断章、アフォリズムみたいなものも作りますね。
岡井 そうそう。彼はちょっと哲学好きなんだけど、いわゆる西洋哲学ってちょっと難しいでしょう、あの難しさ、抽象性はあまり好きじゃないんだよね。
平出 そうですね。「瓢簞のもっとも大きなものともっとも小さなものと二つあって、その容量の差は大きいといっても、大きな瓢簞の中に小さな瓢簞は入らない」とかね、そういう哲学ですね(笑)。「コレヲ瓢簞相容レズト云フ」とかっていう、そういう哲学ですから。
岡井 アイロニーをきかせているな。それは俳諧精神ですね。
平出 そうですね、絵も描いたりして。それは瓢簞の絵とセットになってくるような哲学です。おそらく彼は「これが哲学だ」と思って、「こういうものをやりたい」という時期が中学時代からあったと思うんですけど、上京してきて大学に入ってみると、哲学っていうのは全然違うもので、頭が痛くなった。
岡井 あの当時の哲学って、何を教えたのかなと思うんだけど。やっぱりカントですかね。
平出 先生はドイツ人でしたね、たしかブッセという。それで「何が何だかわからない」って。
岡井 ケーベルみたいなああいう人ですね。ケーベルはたしかに東大で教えてたから。
平出 「こんなに分らぬものなら余は哲学なんかやりたく無いと思ふた」というまで、かつて憧れたイメージとの違いにぶつかった。
岡井 彼だとやっぱりカントですな。カントはちょっと……。
平出 もう頭が痛くなって、「脳病」だとかって言ってますね(笑)。自分で思っていた哲学ではないというところから別のものを探し始めて、審美学、つまり今でいえば美学とか芸術学ですね。そういうものが自分の探していたもので、この辺でもう、文芸と美術は同じ根のものだという思想が、あるいはスタンスが現われてくるのだと思います。それを知ったときに非常に安心したということを語っていますね。同時に、文芸は美術の一部だという考えをたしかに持った。
岡井 俳諧そのものって、あれは美学の話ですね。まさに芸術学ですよね。僕は『俳諧大要』というのがとても好きで、一番驚嘆するのは、何で二十八か九であんなものを書けるのだろうかと思うのね。あまり親しみやすい正岡子規というのは作り上げない方がいい、やっぱり相当の人物じゃないのかな。高いですよ。
平出 そうですね。分類法だったり百科全書的な思考だったりするけれど、ジャンルがどういうふうに見えてくるかという、その変化が彼の生涯の中でダイナミックにあったような気がするんです。最初は哲学に行きたいという憧れもあっただろうけれど、もう世の哲学はそうじゃないというときに、その形式の殻はあっさり捨てる。しかも自分の初発に抱いた実質は捨てないで探しはじめると、未知の分野のありようが見えてくる。これは碧梧桐が『子規を語る』の中で書いていますが、晩年の病床で漏らした言葉の中に、「哲学でも文学でも今までわからなかった問題が驚くほどはっきりして来た。自分でも驚く程だ」とあります。見えて見えてしようがなくなった、だけどそのときにはもう形に表わす体力がない、残念でしようがない、と涙を拭ったそうですね。その「見える」というのは哲学とは、文芸とは、ということだけではなく、それらの広がり方とか相互の関係の仕方とか、そういうものがすっきり見えるというふうな言い方だったように思いましたね。
岡井 平出さんが解説をお書きになった、碧梧桐の思い出話の本ですか。
平出 そうです。
子規の啓蒙──「ぬべし」と「なり」
岡井 俳句の話をちょっと。平出さんはどういうふうに思っておられるのかって思うんだけど、一般に、虚子の宣伝にのせられたせいもあるけれど、子規の俳句はわかりやすくて、いわゆる子規のお弟子さんたちが昭和の年代になってから、たとえば四Sと呼ばれるような人たちが、山口誓子にしても水原秋桜子、高野素十にしても、人生観だとかいろいろなものを付け加えて、それがさらに中村草田男や西東三鬼に至るといわゆる近代の、それこそ現代詩のきらびやかさをずいぶん付け加えたものが増えてきて、そういうもので育ってくると、あの「鶏頭の十四五本もありぬべし」は、何言ってるんだよ、っていうことになっちゃう……っていうふうに、割合このごろはみんな言わなくなって、何かわかったような顔をして言ってるけど、一時期までは評価が低かったわけですが、そこはどうですか。
平出 「鶏頭」の句のことは別にして、子規の句の評価が低い理由というのはある程度わかるなとは思うんです。というのは、やはり子規の句業全体をみたとき、修業時代っていうものがかなり長くありますね。それで明治二八年ぐらいになってやっと本筋に入って行くというか収斂していくというか。いろいろな出鱈目な遊び方で「拙速を競う」ようなやり方で、虚子と碧梧桐を仲間にして、遊ぶようにして作っていた実験時代のものが結構たくさん残っているでしょう。
岡井 何か仲間で集まってやっていましたね。
平出 そうなんです。だからそういうものも、また記録魔の子規が句集に入れてしまいますからね。そうするとたしかにその辺を見ると「何だこれは、大したものじゃないじゃないか」というふうに見える部分があることはあると思うんです。けれど、そこにすでに子規の月並嫌いというか、それがはっきり出ていて、それが重要なんだろうと思うんです。月並批判というのをあれほど最初から徹底してやったというのは……
岡井 あれは芭蕉批判につながっているんでしょうね。芭蕉の門人たちにどんどん月並み化していったのがいたりする、あの月並みっていう定義は、単に平凡っていうだけではないですね。
平出 嫌味ということとか、臭味ということになるんですね。
岡井 あ、そうか、臭味とかね。
平出 ええ。それから説明臭とか。
岡井 玉城徹さんの話にまた戻るけど、僕なんかが驚いちゃうのは、「あたヽかな雨が降るなり枯葎(かれむぐら)」っていうのは一八九〇年ですから、いま平出さんがおっしゃった習作期の作品で、まだ二十三歳ですね。そうするとこれをね、「今日の読者はもはやこの句に対して何の驚きもおぼえないのかもしれない、そう思うといささか責任の念に襲われる」と言って玉城流に悪口を言っているんですよ、われわれのことを(笑)。「目をやるとそこに枯葎の生えた町の一角が見える。薄暗い影を帯びたその枯葎が、今日は何か少し動くようである。長い冬も終わってあたたかな雨がその枯葎の上に降るのだと、そのときに心づいた。何の理屈もなしにその感覚の喜びがここに句として現われている具合である」と。特に「あたヽかな雨が降るなり」っていうのがすごい大事でね、これを断定だなんていう馬鹿なことを言う人がいるけれど、あれは学校文法でね、そういうものに欺かれちゃいけない。そして「何だろう」っていう疑問がまず動いて、それに対する発見の心持ちが「あたヽかな雨が降るなり」って、あたたかな枯葎が動いているんだというところを言っているのであって、この感覚の主体としての自然の人間、すなわち理屈にとらわれた月並み……、月並みっていうのは理屈の俳句だと、それで子規がやったのは、そこで枯葎が動いているっていうところにふと自分の感覚が行く、それを表現したのであって、啓蒙の仕事がここにもあるんだと。子規は「江戸俗臭の芭蕉に対する宗教的人格的気配と闘う必要を痛感したのであった」と言っていて、だからそれはわかるんだけど、「あたヽかな雨が降るなり枯葎」が二十三歳の習作作品とかたづけていいのかと、はっきり疑う。それで一番最後が「鶏頭の十四五本〜」がありまして、これを虚子が岩波文庫の子規句集からはじいちゃった、それに対していろいろ言って、それはともかくとして、とにかくこの「鶏頭の十四五本もありぬべし」という明治三十三年の句は「もう俳句とは呼びえない、『新しい詩』ではないか」と。それで「そこから出発すべきであった」と言って、この一行の詩の生命は、さっきの「なり」というのと同じように、終わりの「ぬべし」というところに集中しているのであって、「十四、五本もあろうかという、そこに作者の精神の鋭い働きが見えるのである」と言って、「感覚美」というような形でまとめているんですが、玉城さんの解釈も含めてどうですか、こういう言い方は(笑)。
平出 大筋で、玉城さんの言われる立場には、私もとても近いものですから。
岡井 ねえ。納得しちゃう、読んでると。「その通りだよ」と。
平出 それとそこにあるのは、一つは玉城さんの発見だと思うんですけれど、子規の虚子宛の手紙の中の言葉ですか、「若し永久のものを求めなば別に一体を創するにあり」という。
岡井 あ、そうそう。
平出 つまり俳句も短歌も永続しない、新体詩は日本のものとはいえない、「別に一体が必要なんだ」ということを手紙で言っていると。これを見つけ出したのは、玉城さんの大変な発見だろうと思うんです。
岡井 大変な発見ですね。
平出 それが鶏頭の句につながっていますね、おそらく。
岡井 そうそう。
平出 その「ぬべし」とか「なり」が作り出すもの、それを私はむしろ、散文と詩の接触点と呼びたいんですけれども。
岡井 だからこの『病牀六尺』の一番最後、死ぬ寸前の、この一二六や一二七の辺のたった数行の、たとえば「蚤虱馬の尿する枕もと」というのは芭蕉の句なんだけれど、それを臭気、臭い、つまり「馬の尿する」というところから鼻が嗅ぎ取る嗅覚的な存在というものを持ち出して来て、それでいつぞや動物園に行ったときのあの動物園の臭さというものをしきりに言って、これは何を言っているかというと自分の体が臭いので、今の病床の最期のこの臭味というのは、……嗅覚というのはすぐに慣れますから本人はもうわからなくなっちゃうんですね。ところがよその人が入ってくればすぐ感ずるわけで、だから律さんや八重さんは毎日感じていたんですよ。それをこの「蚤虱馬の尿する枕もと」とくっつけてね、これは一つの散文詩だと思いますね。それこそ「別に一体」という感じがしてね。
平出 そうですね。散文から生れる詩というものがあるんだな。
岡井 いろんな意味で「別に一体」で、だから平出さんがいろいろ試みておられるし、表現者そのものもそうだと思うんだけど、妙にジャンル分けとかああいうものはどうなんですかね、つまらないじゃないですか。
平出 そうですね。岡井さんが「現代詩」を書いて騒がれる。「短歌」の巨匠が「現代詩」を書いた、という騒がれ方ですね。実質的に見ればもっと違う角度から感じられるはずの作だと思うんです。「短歌」の中で、すでに「別」への手探りがあるわけですから。
岡井 そうそう。平出さんが『弔父百首』を作ったとか、そういうことばかり言っているんだよね。
平出 ああいう反応ばかりですね。そこにすでに「別に一体」を手掛けているのでは、という目が欲しいんですけれども。
岡井 だから何と言うか、伊良子清白を、つまり平出さんはどういうふうに書いたのかという、丹念なお仕事であるとか何て言うか、明治時代の、たった一冊『孔雀船』だけ残した詩人で、あとは短歌を書き続けていたお医者さんという人間に迫っていっている平出さんのことを問題にしなくて、「労作である」とかそんなことばかり言っているんで(笑)、もうちょっと別の見方をしませんかねえ。
平出 そうですね、まああきらめてはいますけど(笑)。ただやっていくことは自然に、いろいろ角度を変えてつながっていきますからね。
岡井 それで一人の人間が単純なことを考えて生きているわけでもなければ、もともと一個の人間というのは総合的な精神の存在なのであって、感覚だけで生きているわけでもなければ頭だけで生きているわけでもなくて、欲望で生きているわけでもないと。そういった見方をもうちょっと子規に対してもしてあげた方がいいような気がするんです。
平出 やっぱり形式に対する意識を、いわゆるスノッブな作家や詩人がもう本当に固めてしまっていますね。彼らにとっては定型と形式って同じような意味ですけれども、子規ならば、形式というものは切り替えとかエッジとかであり、むしろ形式から形式にわたるときに現われるもののことを言ったりする。そういう意味では詩人批評家という言葉が一番ぴったり来るんですけれども、岡井さんがときどき名前を出すベンヤミンみたいに、断章の方法とか形式の断絶に対して自覚的ですね。
岡井 ベンヤミンもそういえばそうですね。総合的芸術家ですよね。
平出 ええ。朔太郎とベンヤミンを重ねる人もいるんですけれども、僕にはそれは何かえぐいものしか来ないんです(笑)。むしろ子規とベンヤミンを重ねた方が親和する。
岡井 朔太郎も相当いろいろな意味で膨らみのある人物で、いろいろなことに手を出した人なんだけれども、たとえばあれだけ若いころに斎藤茂吉を二重思想だと悪口言ったわりには、自分が短歌から出発しているのに置き去りにしてきて──あれは当時の詩壇全体の風潮だったのだろうと思うんだけど──もうちょっと、短歌なり俳句なりというものに対して広い見方をしてもよかったのじゃないか、そこは何だか狭いですね。
平出 狭いですね、蕪村に対してもかなり狭いですね。
玉城徹「活動する精神」
岡井 だから蕪村で思い出したけど、子規の「鶏頭の十四五本もありぬべし」とか、十年前の「あたヽかな雨が降るなり枯葎」にはかなり差があると僕は思うけど、この間の蕪村の発見というのは割合大きいのではないですか。
平出 そうですね。古本屋から本が上がって来て蕪村を読んで、明治二十九、三十年ですか、毎月やっている句会の中でその発見がどう出てくるかというのをいま調べているんですけど、実はすぐは出てこないんです、蕪村の影響って。
岡井 ああ、そうですか。例のみんなでやる、蕪村の俳句輪講?
平出 輪講の掲載は『ホトトギス』ですね。
岡井 あ、『ホトトギス』か。
平出 子規はつねに中心の存在だから、まわりにいくつかが同時に動いていますね。月例の、子規庵に集まってやる句会があるのと別に、郵便回覧でやる十句集の句会があって、それぞれ参加者が微妙にちがいます。この郵便句会の中でどれくらい蕪村の影響が出てくるかというのを、月の順に調べているんですけど、なかなか出てこないんです。「蕪村を発見した」って騒いでいるんですけど、実作の方にはなかなか蕪村風が出てこないんです。やっぱり二年ぐらいはかかるんじゃないかなと思いましたね。
岡井 まだあのころは蕪村研究なんていうのは全然で、第一句集はやっと古本市から出てきたぐらいだから、われわれは簡単に岩波文庫か何かでパッと読めるけど、当時はもうとんでもない、誰も知らない世界でしょう。その中に手を突っ込んで一句一句解釈を広げていますよね。
平出 ええ、一句一句ですね。
岡井 やっぱり子規みたいな人が一人真ん中にいると違っちゃうんだろうな、きっと。
平出 それから、鳴雪みたいな人がいて。
岡井 ああ、内藤鳴雪。鳴雪ってあれはかなり子規に対しては厳しいですね。少し上だから。ああいう人がいるのはいいんじゃないですか。
平出 そうなんですよ。それで鳴雪と自分は俳句に対する鑑賞眼がほぼ一致していると子規は言う。それほど議論を重ねてきたわけです、寄宿舎の舎監だったでしょう。舎監の方が俳句の弟子になって、面白い関係ですけど。だけど議論してこれはいい悪いというのはほとんど一致するようになっていたという。ところが、ある一句について評価が分かれて、どうも同じ句に対して全然違う見方をしているな、と気づく。それもまた議論することによって気づくわけですね、子規と鳴雪は。相当な議論好きだし、子規はそのことをまた、「地図的観念と絵画的観念」という文章に著すという、徹底した批評家ですね。
岡井 二十七のときに日清戦争に行って大喀血をして須磨から松山に行って上京してくる、あのとき本当を言うと田舎に引っ込んじゃってもおかしくないんだけど、もう一回出てきますね。すると仮に二十七だとすると七、八年。脊椎カリエスでからだに穴が開いちゃって、そこから膿が、結核菌の場合は冷たいんですよね。それが毎日みたいに流れる、それを律さんとか八重さんとかが、あるいは宮元医師がやって来て、膿をとり布を替える。病床六尺に閉じこめられてしまっているような人が、何であれだけのことをやれるんですかね。本当に驚嘆すべき人でね、それは意志があったからとも言えるけど、子規っていうのは自分の感情やら欲望に割合自然にしたがう人だけど、とにかく毎日みたいに『病牀六尺』を書き、おっしゃったような句会に出、あるいは人力車の上に仰向けに寝かせられてでも藤の花を見るとか、ああいうやはり二十代の青年から三十四歳十一か月までの、いわば今で言うと青年の若々しい力だったのか、それとも子規という人は変人だからああいうことができたのか、どうなんですか。
平出 いずれにしても「活動する精神」という、これは玉城徹さんの言葉ですが、どこまでも活動する精神ですね。
岡井 そう。だってどう考えてもあの子規全集、あの量は一生かかってもなかなかできないでしょう。しかも質も高いんだもの。
平出 俳句研究の過程で相当悪くしていますね、身体を。ベースボールでもそうですけど、短歌のときはもう横たわっているわけです。「ベースボールの歌」はむしろ、運動ができなくなったゆえにそこにボールの躍動みたいなものを捕まえている。そういう意味では、玉城さんの「活動する精神」という批評の言葉にとりあえず預けてしまいたいですね。
絵と書
岡井 さっきちょっと言ったけど、彼の絵はどうですか。平出さんはご専門だから。
平出 これも驚くべきものだと思います。それで中村不折という画家が絵の具をくれたり、出入りの床屋が鉢植えをくれたり。
岡井 そうだね。
平出 それから美術論の議論をしてお互いにへこまし合ったりするという、そういうところも不折ともども活発ですけれども。
岡井 浅井忠とかね。
平出 そうですね、そういう中で筆をとるわけですけれども、ただ最晩年に絵を描き始めたというのは間違いで、子供のときにすでにもう、名前は出ていませんが北斎の、絵の描き方の本を一冊手に入れて、それを全部描き写すという、そういうこともやっていますから。
岡井 そうですか。
平出 それともちろん、筆文字における筆の使いはすでに幼少からありますね。
岡井 パソコンだと全然絵につながらないんですよね。
平出 これからはつながらない(笑)。だから小さいときから筆を使っている人にとっては、文字が絵になるのはそれほど困難なことではないんだなという気がしますね。
岡井 そうだね。それと、漫画っぽいやつとそれからすごいリアルなやつと、両方ありますね。これはどうなんですか。
平出 俳画は俳人ならある程度こなしたんでしょう。でも、それは概念的な素材や類型の筆致。子規はその方向ではない、彼のいわゆる写生というものの方へどんどん近づいていく。物を置いて、それを見る。見えるものにしたがってのみ筆を動かす。枕元でしか物を見られないので、届けられた草花を描くということですね。
岡井 かなり丹念に、相当時間をかけて描いていますね。
平出 しかも、寝返りも打てない状態で。
岡井 仰向けで?
平出 ええ。最後は寝返りも打てないようでしたから、やはり上を向いて描いたと考えた方がいいでしょうね。
岡井 あの綱につかまったりして。律さんか誰かが紙を持ってやって。それにしてもこれは客観的に見て、やっぱりいい絵だなと思う。
平出 子規の文字のよさもありますけれども。
岡井 ありますね。子規の字はいいですな。
平出 率直でのびやかな、いい字ですね。飾りがない、月並を嫌う、臭味を嫌う、そういうところへ、絵の方でも最終的に行くんですね。朝顔の絵なんか好きですね。「朝顔や絵の具にじんで絵を成さず」と同じ絵の具の筆で句を付けたりして。
岡井 ただ、もともとの『仰臥漫録』には、漫画みたいなのもあるんですけどね(笑)。専門の絵描きさんたちも、これを見て素晴らしいと言っておられるみたいですね。
平出 ええ。線の潔さ。
岡井 やっぱり人間って最後にこういうスケッチを、あんなに厳しい身体的条件の中でも、『病牀六尺』のようなああいう非常にすぐれた、ある場合には短篇小説みたいな、あるいは散文集みたいなものを書きながらこういうものも描くというのは、人間の行為としてはどういうことなんですかね。
平出 それについて直感的に思うのは、あの『仰臥漫録』のオリジナルの形状ですね。
岡井 ああ。二冊綴りですね、あれは。
平出 半紙を部厚く綴じて、その白の状態に描いていく。子供の絵日記と同じだと思いますが、ところがそこにフランスの浅井忠から来た絵葉書を貼りつけたり、菓子パンや缶詰のラベルを描き写した、そんな立体感あるおもちゃ箱的な部分とか、食事や睡眠の記録のような、日誌の要素が増えてきますね。そうするとますますそれが本に置き換えられないもの、一冊きりで終わるものになっていくと。ここに何か秘密があって、虚子などが「面白いから『ホトトギス』に載せませんか」と言ったらものすごく怒って。
岡井 そうらしいですね。
平出 「いやこれは自分の楽しみでやっているんだから」と渡さない。でも、亡くなった後に復刻されて岩波から出たり、最終的には岩波文庫になったりしてくると、最初の状態は見えなくなりますよね。
岡井 そうですね。あれは復元されていないんでしょう?
平出 今はされていないですね。虚子記念館が建って、そこに本物があります。
岡井 今は復元技術なんてすごく進んでいますから、同じような紙を使って復元してみんなで一遍見てみるといいな。
平出 そうですね。二分冊になっていて、二冊目はやはり病が篤くなってくるから白いページが増えてきますね。その変化も胸を打つわけですけれども。
岡井 あれは終わりの方は俳句がずらっと並んだり、例の顕微鏡の絵が出てきたりしていますね。まさに病床のノートですね。
平出 そうですね。それで二冊目に時刻だけが出てくるあたりがあって、それが不思議だなと思って考えたんですけど、あれは痛み止めを打って覚醒した時刻でしょうね。
岡井 あれはモルヒネの注射日記ですよね。それで一冊目と二冊目の境い目の本ですか、例の自殺の……。
平出 ええ、一冊目の最後ですね。
岡井 しかも何か知らないけど、なぜあんな刀の絵とかをわざわざ描くんですかね。ああいうところが実に何というか。あの文章は非常にいいんですけど、「自殺しようと思ったらお母さんが早く帰りすぎちゃったんでできなかった」という理屈をつけているわけで、そんなことを言ったっていくらでもその気になればできたはずなのに、しなかったっていうことを書いているわけだけれど、あれは自分が今どういう状況にあるかということを自己分析しながら書いたのだろうという感じがしますけれど。
平出 「逆上す」という言葉が出てきて、それを見ている自分との対比が印象的ですね。
岡井 じゃあその後死ぬまでの間に自殺の記とか何回か出てくるかと思うと出てこなくて、一冊目の終わりだけで。
平出 そうですね。
岡井 不思議な感じだな。
平出 むずかしいところですね。
「〜すわれは」と「〜ところ」
岡井 もう一つ聞きたかったのは、さっきおっしゃっていたことかな、文士の問題です。また玉城徹さんが「何でもかんでも子規ほど書きに書いた男はないと思われる」と言っていて、「文士の模範としなければならない」と、つまり文学が資本主義の発達に伴っていずれは商品化していく見通しというのは甚だ面白いと言わねばならないとされる。れいの「吉原の太鼓聞こえて更くる夜にひとり俳句を分類すわれは」というのは有名な、さっきから言ってる俳句分類の話だけど、これは明治三十一年の作で、文士の自画像と言ってもよかろう。「何々すわれは」という結句は、自分はこういうものだと名乗り出る形である。それ以外の場合にこの形を用いるのは空疎であり不愉快である、と言っているんですけれども、僕はときどき作るから申しわけありません(笑)。玉城さんにもうしょっちゅうお辞儀してるんだけど、「申しわけありません」とか言って、玉城さんの言うことを次々と裏切ってきたわけですから、それでいながら玉城さんの歌は大好きなわけで、向こうとしても「付き合いにくいやつだ」と思ってると思うんだけど(笑)。それで「文士の孤独な句業はそのまま主観的に詠嘆されることなく、自画像として客観化されて一個の詩として結晶した。実に驚くべきことである。子規はそれまでの伝統的な短歌の枠を打ち破ってそれとは類を異にした新しい詩としての短歌を発明したのであった」というのが玉城さんの見方で、やっぱり今われわれはみんなそうなんだけど、文筆で食べている人間というのはみんな商品化したものを売っていますよね、いろいろな形で。それの中でやっぱり子規というのは一番最後にそれを意識して、それでそういう自分自身というものを資本主義社会の中の文士というのではなくて、もう一つ先の、「ひとり俳句を分類すわれは」なんていうのはお金にも何にもならないんだけど、そこのところに自分自身というものを、新しい詩としての短歌というのを発明したのだと玉城さんは言うんだけど、この意見はどうですか。
平出 ちょっと世の中の中心部を離れているんでしょう(笑)。
岡井 ねえ。われわれに向かって皮肉を言っているんですか。
平出 これはずいぶん現代短歌批判ですね。
岡井 すごい現代短歌批判で。で、当たってるの。
平出 ええ、ほとんど現代詩批判でもあると思いますけれどもね。
岡井 当たってるところはありますよ。
平出 そうですね。
岡井 だから玉城さんにも「おたくもそうじゃなかったですか」とひとこと言える(笑)。
平出 玉城さん独特のスタンスです。まあそれはおそらくご自分も意識していたと思いますし、自己批評も含んでいるかもしれませんね。この「〜すわれは」というのも、たしかに岡井さんもかなり使われるし、しかし玉城さんの歌にも出てきます。「あれっ」と思って読んだ記憶があります。
岡井 普通はね、「〜にけるかも」というのと同じで多少のアイロニーやユーモアを含めて「〜すわれは」で言わざるをえない。われわれは明治時代と違うから、照れながらアイロニーで言っていることが多いですよ。
平出 もともとこの語法はどのくらいさかのぼれるんですか。もちろん鷗外にもありますが。
岡井 やはり橘曙覧の例の「たのしみは〜し時」っていう形の「独楽吟」百首くらいというのがありますよね。あれでしょう、きっと。
平出 あとは「〜するところ」というかたちで終る、絵画を見て詠む歌というのは?
岡井 そうそう、あの「ところ」っていう押さえ方はうまいんじゃないですか。やっぱりあれは子規のオリジナル……。
平出 発見ですか。
岡井 そうでしょう。それを斎藤茂吉が真似したわけですよね。あれも日本画か何かを見ながらね。
平出 釈迦が死んで動物たちが泣いているところとかね、「木のもとに臥せる仏をうちかこみ象蛇どもの泣き居るところ」とか、そうやって別の絵に移り、次々に「ところ」にしていくという、あれは一つの短歌修業法みたいなところもあるんでしょうかね。
岡井 トライアルとして「ちょっとこうやってみたら」って、明治三十一年の「足立たば不尽の高嶺のいただきをいかずちなして踏みならさましを」っていうのが七首この歌には出てますけど、この辺から、「ひむがしの京の丑寅杉茂る上野の陰に昼寐すわれは」とかいうのがあの吉原の俳句分類の「われは」と同じように、これは多分十首あって。「なむあみだ仏つくりがつくりたる仏見あげて驚くところ」っていうのは仏作りと仏さまがあるとか、「もんごるのつは者三人二人立ちて一人坐りて盾つくところ」とかっていうこういう歌ですけど、なかなかうまいんでね。最初にやってしまったとしては、かなりいいところまでもうすでに行っているんで、何かこういうテーマというとおかしいけれど、一つの切り取り方で感興をおぼえちゃうと、ずっと次々に作っていくときの子規の作歌力というのはすごいんじゃないですか。
平出 躍動していますね。
空間的興味の連作
岡井 この人は躍動しますよね。それで次々に頭に浮かんでくる、それがもう楽しくてたまらない(笑)。
平出 楽しくて仕方ないっていう感じが来ますね。それで角度を変える。
岡井 そうそう、角度を変えるんですね。その角度の変え方がどうだって言うんでね。そこで一つの単語を使うか使わないかとか、一番有名なのは藤の花の一連なんですけど、あの藤の花の一連だって、最初は「たたみの上にとどかざりけり」だけど、途中から藤の花を去年見に行ったとかそういう話になったり、それから古の藤の花のところへ行ったり、ということは十首なら十首作るときに、いろいろな要素を入れる方が全体の完成度は高くなるよということを、ちゃんと知っていてやっているわけですよね。
平出 そうですね。子規が俳句を学生時代にかなり意識して作ったときですか、どんどん湧いてきてしようがない、ところが紙がなくなってしまってふと見るとランプの笠があるから、それに書いてやろうと。すると笠が十二面なので、じゃあこれは十二句で完結させてやろういうところで十二という数字を自分に対する縛りにしたり、逆にそこで躍動を作ったり、あるいは十二か月という季節のめぐりを捕まえたりという、そういう運動神経ですね、句作りの。
岡井 そうそう、運動神経です。まあ連作の問題というのがあって、玉城さんは連作反対派でいろいろ言っておられて、だから子規がたとえば一番最初に作ったのは、あの「松の葉っぱに雨が降っているところ」のやつだけれど、それを非常に大きく取り上げて、弟子の伊藤左千夫は連作連作、って叫んだのだけれども、本当だろうかというのが玉城さんの疑いで、「いや違うんじゃないか」というふうに言うんです。でも先ほど言いましたように、「瓶にさす藤の花ぶさみじかければたたみの上にとどかざりけり」の前に非常に「面白い夕餉したゝめ了りて仰向に寝ながら左の方を見れば」という、この岩波文庫ですと七行の中に散文がまずありますね。散文が非常にきれいですけれど、それで十首あってその後で、「おだやかならぬふしもありながら病のひまの筆のすさみは日頃稀なる心やりなりけり」「おかしき春の一夜や」というところまで行きますね。私は『正岡子規』を書いたときに、この全体を見なきゃだめなんで、「瓶にさす藤の花ぶさ」だけを見てはだめで、全体の構成力というか、しかもこの前書があって後書があるというこの全体のコントラストのよさというか構成のよさというか、これを見なければいけないんだよと言ったんですが、これはだから連作っていう言葉を使うか使わないかは別として、言ってみればこれだけになると、もう十首の歌というよりは、十首の歌プラス前書・後書だと僕は思うんですが、そういうことを言ってないで、たとえば「瓶ににさす藤の花ぶさ一ふさはかさねし書の上に垂れたり」という一首なら一首を丁寧に観賞するということの方が大事なので、子規は子規なりにあちこちの角度から歌ったのであって、一首一首が独立した作品なのだから、「藤なみの花をし見れば紫の絵の具取り出で写さんと思ふ」という一首はこの連作の中にあろうがあるまいがちゃんとした一首として見なければならない、というのが玉城さんの考え方のようですね。私はこれは両立し得るかなとは思うんですが、しかし意外な影響力を近代短歌に、伊藤左千夫が言うところの連作に、子規自身は「連作」なんていう言葉はひとことも使ってないけれど、要するにひとかたまりのものとして呈出するというときの角度の問題で、いろいろ切り口を変える作り方というのが、斎藤茂吉が一番それを上手に自分流に組み替えて使ったんですが、近代短歌は、われわれが前衛短歌と言われるようなそういうところに至るまで、現代に至るまでこれを踏襲してきて、これでやっと 現代詩とかあるいは散文に対抗できているんじゃないかというのが私の考え方なんですけど、どうなんですか、そういう点は。
平出 ひとつは空間的興味が子規の中心だったと思います。一首と一首とのあいだに決定的な断絶を作りますね、子規の場合。興味の中心はあくまでも空間的なことで、連作の形はとっているけれど、それは角度を変えながら、または断絶を織り込みながら空間に迫ろうとしているような、そういう衝動ではないかということが思われますね。ところが往々にして詩歌が連作になるときは、時間的興味だとか連続的な運びとかっていう話になってしまうと。
岡井 そうです。だからたとえばご飯を食べ始めて食べ終わるまでだと十首にするとか、そうすると間で角度は変わらないんですよね。
平出 そうですね。
岡井 そうか、玉城さんが言っているのは、そういう時間の流れにしたがって作るというのではなくて、角度を変えながら……。
平出 一瞬ごとに空間的興味で、角度を変えながら迫っていく、作りなおしていくというとらえ方なんですね。
岡井 それはしかしある意味から言うと、そういう連作の作り方をしている人がいないわけではなくて、僕なんかもそれなりに意識してそれはやっていますから、そうすると連作あるいは連作反対という話ではなくて、もっと違う観点でとらえた方がいいんですね。
平出 ええ。伊藤左千夫の連作というのは、どちらかというと時間的な要素が勝ってくる。
岡井 そう、連作の定義がまず同じ時間帯に作られてみたものを、そこから出発しているからそうなっちゃったのは、一番最初の明治三十三年の「五月二十一日朝雨中庭前の松を見て作る」というので「松の葉の細き葉ごとに置く露の千露もゆらに玉もこぼれず」という、松の葉っぱに雨露がついているというだけで十首作っているわけで、これから出発しちゃったものだから、同じ時間帯で同じものを見て、それでもし懐古的な作品が入ってもそれはそのときに作者がそのことを考えついたという、そういう同時性というようなもの、それからあとは材料の統一かな。たとえば今で言うと松の露とか藤の花とか材料が一致しているわけで、ちょっと忘れてしまいましたけれども左千夫の連作の定義があるでしょう。それは明らかにおっしゃるように時間性をすごく大事にしている。空間性よりは時間性で、左千夫はつくっているんじゃないですか。
平出 左千夫の言う連作に対する批判が、玉城さんにもあったということですね。
岡井 そう。左千夫の考え方は、子規の本質をつかんでいないというのが玉城さんの考え方でしょうね。それはそうだなとは思うんですけどね、そういう点では子規のはよほど空間性を重視している。
平出 特に物と物との関係への視線というのは、詩人、歌人、俳人という枠が取れてしまうぐらい、激しいものがありますね。造形性というか、美術家としての子規という面が出てくるような。
子規の継承
岡井 大概のことを聞いたけど、最後の「別に一体」という枠組みは現代詩、あるいは現代文学にすごく大きいと思うんですけど、その子規の考え方というのはどう思いますか。
平出 それは形式を踏みはずす力だと思うんです、踏みはずす意志があるかないかというところで成り立つので。これはやはり、形式の経験を十分積まなければいけないという面と、それから踏みはずす意志というものと、先ほどの運動神経、さらには散文精神や批評精神がセットになって初めて実現するわけですから。
岡井 そうでしょうね。
平出 子規みたいな人は割と自然体でやったように見えるんですけど、相当に強い判断力と直観力があったのではないかと思います。これは今日ではなかなか共有できないかもしれないという気がするんです。岡井さんが最近、ああいうふうに「自由詩」をつくられて、まあ現代詩の連中は評判にしているんだけれども、それを違う言葉に置き換えてしまうわけですね、「この形式もできる」「こっちの形式もできる」「現代詩にも来てくださった、すごいなあ」みたいな。そういう話じゃないと思いますね。いまは自分の選んだ形式に満足したい人ばかりで、困った状況です。
岡井 一番はっきりしているのは、やっている本人がそう思ってないわけだから(笑)。全然そうじゃなくて、自然に詩が出てきているのは、それを僕はまあ自分では絵は描かないからあれだけど、正岡子規っていう人はたった三十五になるかならないぐらいのところで実践もしたし、それから認識も非常に明確であったという稀有なあり方。
平出 稀有ですね。
岡井 これが何だろう、現代で単にあちこちに手を出して、マルチにあれもやる、これもやる、ってやったらそれでできるというわけでも何でもないわけで、その一つ一つがちゃんと到達していなければだめだろうし、その「別に一体」というのは百年前の子規がわれわれに与えてくれた宿題みたいなものかなと、それで今は見ていたらわかるけど、文学あるいは文学魂とか、玉城さん的に言うと文士魂だけど、もう非常に衰弱している時代でしょう、今は。だから子規のそういうことを言ってみたって、何を言っているのかわからないと。それは玉城さんも言ってるけれど、漢詩文の教育を充分積んで、漱石も鷗外もそうだけどみんなまずそれをやって、それから次の段階で俳句を発見し、短歌ができていくということなんで、それはわれわれの世代でももうだめだから。もちろん「漢詩を今から小学校でやれ」なんていう意味ではなくて、教養の蓄積を背負って来れない、非常に困難な時代じゃないですか。ただ現代詩を読んでいても現代短歌のあの若い人たちのを読んでいても、器用にこなしていて面白くないとは言わないけれど、やっぱり僕は子規の言う「別に一体」というようなものを実現していくようなね、初めにジャンルありきじゃない、逸脱、横溢の躍動がみたい。でもほとんど理解者がいない仕事なんだろうね、そういう作業というのは。それが果たしてできるのかできないのか、案外すごい、日本の詩歌の世界だけではない、大きい問題かもしれませんね。
平出 非常に大きな問題ですね。今日はちょうど、先頃亡くなった玉城徹さんの追悼対談みたいな感じになりましたけれども。
岡井 そうですね、本当にありがとうございました。
(おかい たかし・歌人)
(ひらいで たかし・詩人)