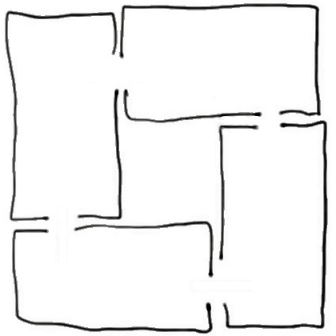随筆と小説とのあいだ
平出隆
(川崎長太郎『もぐら随筆』解説 講談社文芸文庫、2006年)
川崎長太郎『もぐら随筆』は昭和五十二年十一月、エポナ出版という小出版社から刊行された。著者の「あとがき」によれば、収める随筆は「ざっと二十年間」にわたり、文芸雑誌や新聞などさまざまなところに書かれたというが、本書には初出の記録が収められなかったので、今日の読者は、とくに時間においてとりとめのなさ、ときには小さな混乱を味わうかもしれない。
「もぐら随筆」と名づけたのは、これも「あとがき」によれば、「世間を狭く生きてきた男の呟やき」という意味合いという。ここでいう「呟やき」が「随筆」ということにあたるらしい。
随筆といっても、私小説家のそれである。
あるいは川崎長太郎は、私小説家とはもぐらのごときもの、と考えていたのかもしれない。とすれば、この書名は、「私小説家の随筆」という意味ともなりかねない。
その私小説作品を読んできた者には、この本の各処には親しい世界が広がる。基となるものが「私小説」であるから、登場人物は私とその周辺ということになり、その作家の随筆であるからには、それと離れぬ、ほとんど見知った世界が広がるほかないのである。
では、これらの随筆を小説の副産物といって済ませられるかというと、どうして、そういうことではない。小説と生身とが近い分だけ、その余禄としての「呟やき」は、いわゆる随筆、いわゆるエッセイとは一味違うことになる。たとえば、いわゆる随筆というものならいわば書き捨てにしてしまいがちな小説作家の「意気地」のようなものが、ここには漂っている。あるいは、いわゆるエッセイというものなら満足してしまうはずのところで満たされていない。これだからこそあの私小説作品があのようなものであったのか、と思わされもする。
だから、これまでまったくこの作家の私小説を読んでこなかった読者が、これら随筆のほうをまず読んでみて、さてその私小説というものを読んでみようとなれば、それも導かれ甲斐のある筋道であろう。
すなわち、私たちの作家は、じつに微妙なことを平然とやってのけている。ひとつの場所を、ほとんど同じような筆つきで、角度で、しかしよく見ればちがうしかたで描くということを、である。ひとつの場所を、同じような筆つきで、角度で、ということだから、ときとして、ちがいは見えない。ところが、やはり生れてくるものの塊は、小説集と随筆集とに、どうしようもなく振り分けられる。
それにしても、なぜ同じような筆つきで、角度で、ゆるやかに分れるようにして別の次元が書かれるのだろうか。そもそも私小説と随筆とは、異なりながら別々のものなのか、異なりながら連続するものなのか。
そんなことを、この解説という場で、少しは語れたらと思うのだが。
「抹香町」物と呼ばれる一連の作がこの作家の、いわばあたりをとった小説作品である。
その抹香町という怪しい場所については、当然のことながら、こうした一篇ずつの冒頭あたりでくり返し語られている。それはおおかたは、舞台として、背景として、細部としてである。
ところが、小説ならざる随筆では、それはどう語られるか、風景として、風俗として。歴史として、記憶として。そういえるだろうか。そんなところから見ていこう。
この本には「消える抹香町」や「移り変りの記」という格好の書き物がある。ここで「書き物」と呼ぶのは、とりあえずは小説か随筆かといった枠を外して読んでみるべきだと思うからである。随筆集の中に「小説」が紛れ込んでいないとも限らない、という目で読んでみたいのである。
「消える抹香町」は、売春防止法が公布から二年がかりで施行され、赤線が廃止される昭和三十三年、その直前の早春に、雑誌「群像」の求めに応じて書かれた。(この掲載の様態について調べていただけませんか。小説扱いでないか、どうか。)
小田原の私娼街として繁盛してきた抹香町も、それによって形を失う。そこまでのことを語るのに、東海道の宿場の女郎屋であった総二階の旅館の並びが、明治の半ばに取り払われ、町の裾のような「新地」に移されたこと、幼年時代にはじめて脚を入れたのは祭の山車を引っ張ってのことだった、という昔日の興味深い体験も語られる。
昔、国道の、両側にあった遊廓は、明治の中頃とり払われ、町の裾回しみたいなところにあたる一画へ移転し、「新地」と呼称されていた。私が、そんな方面へ脚を入れたのは、多分八、九歳の頃、お祭の山車(だし)ひっぱって、皆とともに繰り込んだのが最初であった。ぐるりに、黒く塗った板塀をめぐらして、町家(まちや)と境し、同じ色で塗った門柱のある出入口をはいると、突当りから左右に一列「東海楼」「錦昇楼」「加納楼」その他七、八軒の、同じように総二階で、千本格子のはまった張店(はりみせ)、とりどりの趣向こらした、背の低い塀に囲まれた構えの女郎屋が並んでいた。時は、祭の日だったし、古風に大きな家、装った女達、揃い着てうかれた氏子のはしゃぎ振り等、子供心にもなんか華やかな別天地へ来たように思いなされ、一寸奇異な感招いたものであった。
小説の文章と限りなく近いが、それは都市を、街歩きの視線で描きとめるときの独特の筆致によっている。川崎長太郎の文学の特質のひとつは、都市のエクリチュールであることだ。どんなに古風な男女の人情がとらえられるときでも、それは牧歌を奪われ、金銭と塵埃に痛めつけられた街々とその路傍の陰翳を描く部分を切り捨てない。しかも、その痛めつけられている都市の肖像に、書き手の筆がある種の愉楽をさえた湛えつつ反応しているとき、私たちもこのあてどない歩行に、みるみる巻き込まれていく。
それにしても、八、九歳の少年が「皆とともに繰り込んだ」遊廓の情景は、エッセイの構えであればこそさりげなく出てきたものかと思われもするが、川崎文学全体を思うとき、きわめて象徴的ななにかを感じさせる。
その文学的な歩みは、少年時に図書館の本を傷つけたことから故郷の学校を追われ、東京に出てアナーキズム系の詩人として、また転じては私小説家としての出発を持ちながら、ふたたび尾羽打ち枯らして故郷に戻り、生家の裏手の海辺の物置小屋に住みつく軌跡として、作品においてもくり返し語られてきた。読者には、私娼街としての「抹香町」という舞台への関心ばかり先に立ってくるが、この一連の作物の舞台が、幼年時代とぴたりとかさなっているところはあまり気づかれていない。「抹香町」の主人公は、ほかでもない、幼少より自家のものであった物置小屋から、娼家の並ぶ区域へと脚を運んだのである。と気づくとき、随筆の次のような記述も、私小説の連なりかと思える。
その目的もって「新地」へ脚を向けたのは、大人の分になりかかった、二十(はたち)時分であった。海岸に近い私の家と、遊廓とはかなり離れていたが、風向きによって、そこでたたく太鼓の音など、手にとる如く聞えてき、耳について寝つきにくい思いをしていたようであった。当時、私は家の業に従い、魚籠担いで毎日箱根の山坂登り、温泉旅館へあきないに行くことしており、同じ天秤棒揃え登って行く仲間には、年頃の若者も相当いて、帰り路、行きがけとは嘘のように軽くなった籠振り振り、彼等は女郎買いの話その他、手ばなしに始めるのが、おきまりのようであった。最初は、そんなエロ話きく、こっちの耳までけがれでもするように、辛さをしかじかと父へ訴え、再三彼を困らせたような私も、次第に顔赤らめたり、ムシズの走るような思いを覚えなくなって行き、いつかわれから彼等のざれ口に聞き耳たてるような具合であった。
そこから三円くらいをもって女郎屋へ上がり込むくだりは、私にはやはり随筆の書きかたとしてのみ見える。
はっきりと随筆的なもう一篇の「移り変りの記」には、「童貞」の始末はこんなふうにあらわれている。
板塀で囲まれた一部には、女郎屋が堂々六七軒棟をつらね、相当の繁昌振りだったらしく、殊に第一次世界大戦の好景気時代には、ここにもかなり黄金の雨が降った模様である。十二、三歳時分、揃いの衣装を着、祭の山車(だし)ひっぱって、一同と一緒に私も遊廓「新地」へはいってみたことがあった。中には、土蔵造りの女郎屋もあって、建物が申し合わせたように大きいのに驚いたり、ウチカケと云う派手な上着ひっかけ、顔を塗りこくった女連が、それぞれ女郎屋の入口へ群がり、面白珍しそうに山車をみている姿にも、眼を光らせたりした。が、彼女等が、どう云うことをする類いの女か、もとより知る由もなかった。ひと並みに長ずると、私も童貞ひっさげ、そこへ赴き、まん中へんの一軒に上り込んでいた。今でも、秋田生れだとか云った相手の女の、しぼんだようにほっそりした顔形を、朧気に覚えてはいるが、二回三回と脚を運びながら、毎度味気ないようなむかつくような後味買って、出てくるしかないようであった。
この文章の表情は、しかし私小説におけるそれと、おおよそのところで重なってくるといってもよいだろう。むしろそこで鍛えあげられた書法が、随筆にもさりげなく、あるいは堂々と用いられているといったふうでさえある。
いわば、時代を大づかみしているところでも細部を逃していない書きかたである。骨張った調子だが、助詞の操りや省略によって独特の、こういってよければ散文の音楽が生れてくる。とはいえ、運びは随筆、エッセイのものと決めるほかないのは、どうやら公の場所において保持する筆者としての「私」の儀礼的な立場ということになるかもしれない。
私小説においては、自分をさらに身ぐるみ剥ぐところを、随筆においては、それでは公の場での語りとはならないと、押しとどめるものがあるらしい。
これらの随筆を追っていけば、小田原における娼家は、およそ次のような歴史を辿った。東海道筋の両側にあった総二階昔造りの遊廓が明治中頃に取り払われ「新地」へと移り、第一次大戦の景気で繁昌し、旧風の女郎屋として残っていた。それとは離れて、寺の多い貧しい町家の間に「淫売屋」が生れ、次第に「新地」を凌いで私娼街となり、「抹香町」と呼ばれるに至ったらしい。
昭和初年、この私娼街は名前ごと、地続きの刑場跡に移されたという。「ふだん水がじくじく涌いていたりして、ろくな田にも畑にもならない」ところだったという、この書きぶりも小説家のものだが、加えて、地元の目というものか。
川の変貌、道路の変貌をとらえながら、抹香町の変貌とそれとの付き合いの移り行きが語られていく。それがそのまま、一方では近代日本の風俗史についての貴重な証言となり、他方では一市井人のヴィタ・セクスアリスであり、作家として歩いた精神と感情の道のりをも示す。
ところが筆は、やはり公の語り手を逸れがちとなる。私のほうへ私のほうへと逸れるのである。
「戦争が敗けときまる二年ほど前」には、原稿料の口も途絶え、食物を探すだけでいっぱいになった人は「いつか忘れるともなし「抹香町」の方角忘れてしまい、終戦後もざっと四年ばかりは、その筆法で同方面へ御無沙汰のし通しであった」という。
今思い出しても、終戦前後の、ひとの一生からつもれば、それ程短くない期間、性欲も私娼街もてんで頭にないものの如く暮していたのが、不思議な気がしてならない。その間、私は半身不随の中気病みみたい、僅かに息だけしていたのに過ぎなかったか。
私へ私へと逸れた上でのこの回顧には、むしろその個人性ゆえにこそ、戦中戦後の大文字の「日本人」そのものの呟きがかさなってくるのではないか、と思わせもする。
それにしても、「抹香町」物が五十歳近くで書き起されていることには、あらためて感慨を覚える。それは語の単純な意味で、戦後文学だった。
執筆時点の売春防止法施行の春を溯ること二年ほどの、移行期における圧力の実態についての記述など、関わる者たちそれぞれの心理と算段とまで書き留めて、その資料的価値は第一級のものだろう。
だが、それで終らず、「消える抹香町」は最終段で、馴染みの、「一度はかりにも妻にしようとまで心に決めたことがある」娼婦N子とのかかわりと別れについて、詳細に語りだす。
形式についてのふつうの観念では、「生身の人」が出るのが随筆と思うかもしれない。だが、「生身の人」とはなにか。生身ということばをその字義通りにつかうならば、公的な場所における語り手たる自分を崩すことのできない随筆に、生身が出せるものではない。小説家ならば、切って血が出るそれを、小説のほうにこそ出そうとするのだろうか。ところが、読者のために消尽される小説は、作者の生身を許そうとしない。その許されないところに抗うものとしての、私小説の生成の由縁がある。
とすると、随筆として世間に通じるこの書き物――「消える抹香町」を核とする『もぐら随筆』が明かしてくれるのは、随筆は生身ではない、ということではなかろうか。そして、「もぐら随筆」の由縁は、「私小説家の随筆」という意味合いをさえ超えて、この作家の書くものが、「私小説」にも「随筆」にも収まりきれぬある一途な率直さによって成り立っていることを示すのではないか。
語り手が公の場にある自分を崩せないところに見ることができたはずの随筆という形式の輪郭も、「消える抹香町」では、N子の登場と消滅によって、茫々たる時間をひろげて終る。杳として行方が知れぬのは女ばかりではない。昭和三十三年の春、五十代半ばを過ぎた川崎長太郎は立ち尽している。
その後、おそらくはまったく推測されることのなかったことがもたらされた。読者として物置小屋を訪ねてきた三十歳ほども年の離れた女性と、幸福な結婚をしたのである。
『もぐら随筆』の二十年はじつに変化に富んでいる。初出一覧がないことを幸いに、私たちはこの渾沌を楽しむことさえできよう。冒頭の「梅干の唄」には、いきなりその思いがけない家庭の幸福があらわれ、この懐かしい人格の生来の無垢があらわれる。
第三章の「私小説の半世紀」には、作家たちの仮借ない肖像が並ぶ。これはそのまま、彼らの文学的姿勢を借りて描き出す、多面的な自画像ともなっている。
冒頭の穏やかな老後と終章の作家群像の記憶とのあいだには、第二章として広大な自然への旅と共鳴とがひろがり、ときにはそこに川崎長太郎自身の歌う声が響くのである。
どうも小説を書いている気がしない、という淡々としたことを、晩年の川崎長太郎は吉行淳之介に、ひそかな見解として打ち明けている。
書くということは作るということと、どうやらちがう、と。
小説と随筆とを突き合せて読むとき、川崎長太郎はますます面白い。いやここは一番、作家自身のことばをつかって、面白珍しい、といっておくべきかもしれない。