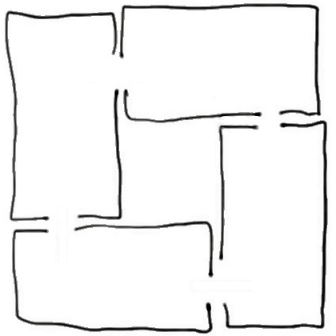本稿は『遊歩のグラフィスム』(岩波書店、2007年)として刊行される前に「図書」誌2006年12月号に掲載された際の入稿テキストである。
平出 隆
遊歩のグラフィスム XXVI
古代・種子・散文
「老いは漸く身に迫って来る」ではじまる鷗外の随筆「なかじきり」には、すぐその先にこんな一節がある。
わたくしの多少社会に認められたのは文士としての生涯である。抒情詩においては、和歌の形式が今の思想を容るるに足らざるを謂い、また詩が到底アルシャイスムを脱しがたく、国民文学として立つ所以にあらざるを謂ったので、
「伊沢蘭軒」完結直後、大正六年の文章だから、この「詩」は一読して、多義的であろう。しかし、そこから「款を新詩社とあららぎ派とに通じて国風新興を夢みた」とつづくのだから、先の箇所でいわれている「詩」とは、やはり漢詩のことを指していた。新詩社の設立は、明治三十二年のことである。
「自らの背後の影を顧みる」のに、小説や随筆のことは措いて、まず詩歌のことを語っている。いろいろな形式にふれてきた中で、詩歌の重たかったことが知られるだろう。けれども、それでさえ、ひとつの形式ばかりを指していない。漢詩、新体詩、短歌、俳句、訳詩とさまざまである。『うた日記』(明治四十年)や『沙羅の木』(大正四年)を見れば、そのかたちの多様さが一目瞭然となる。一目瞭然にすることも、鷗外にとって必要であったととるほかない。
もちろん、鷗外は小説、戯曲、哲学、歴史の各方面での「なかじきり」をも行なっている。そうして、「文士である、芸術家であるという覚悟はなかった」、哲学者でも歴史家でもなく、「終始ヂレッタンチスムを以て人に知られた」という名文句を書きつけている。
こういうものを眺めながら私がことに関心を寄せるのは、鷗外詩歌と日記とのかかわりである。また史伝物とあわせることで浮ぶ、その時間意識である。
いうまでもなく鷗外は、生涯のさまざまな時期に対応する、独立した呼び名のある一連ずつの日記を残したが、それはたんに、自分の生の時間を記録しようという欲求によるばかりではなかった。
「北游日乗」「航西日記」「独逸日記」「隊務日記」「還東日乗」「観潮樓日記」「小倉日記」「委蛇録」――こうやって眺め比べると、すべてにおいて書きかたの変容したことが分る。自分の生の時間を分節化し、それぞれの時節に別々の階調を与えること。結果にすぎないことかもしれないが、鷗外は日記においてそういうことを行なったことになる。
鷗外にとって漢詩とは、もともと日記にふくまれるものであった。少なくとも漢詩文体で書かれる日記に混淆するものであった。初期の漢詩は「北游日乗」などの漢詩文体の日記に残されているものが多い。そうすると詩そのものが、日記に近いところから生れていたということもできるだろう。
また、いわゆる日記とは一線を画すにもせよ、『うた日記』はあからさまに日付をともなった詩作である。これについては、日露戦争という特別な状況を考慮に入れないわけにはいかない。その上で、詩歌が日付をもつとき、それはどんな意味を隠しているのかということは、徹底して考えるべきことと思われる。
ひと時に ひと歌を見よ
わすれても ふたつな見そね
これは巻頭近辺の「ねぎごと」という詩の中の二行である。作者から読者への願いごととは、「卯の花のまだひらかないころのほととぎすが、忍び音であってもひと声で心のすべてを籠めたように歌ったものだから、いちどきに二つ以上読まないでください」という謙遜の意味合いにある。
だが、ここには別の意味合いもかぶさってくる。一篇ずつ一首ずつの詩歌には、非常に強く日付の刻印が押されていることである。「忍び音」の謙遜とは別に、日付と結託した方法への、あえていえば自恃もまたひそんでいないか。さらにはまた、短歌、俳句、新体の詩をこきまぜる方法にも、その自恃は及んでいないだろうか。
私はいろいろな形式に同時にかかわるひとりの物書きというものに注意をしているが、それは別にいわゆるマルチな能力に関心があるからではない。
一人の人間が、どう多角経営的に存在しうるかということではない。そうではなく、時間の流れに立つ一人の人間の中へ、いかなる言語的基盤が流入し、どう多面的に、多次元的にはたらくものか、ということに関心をもつからである。
もちろん、言語は人間の中にだけあるものではない。鷗外の生きた時代から今日まで、言語の形式は人間の外なるものとして劇甚な変化を遂げていった。そうであれば、こんなふうに問い直してもいいのではなかろうか。ひとつの国語のもつ諸領分を、ひとりの言語はどのように構わずに踏み破って歩いていけるのか、と。
人間を消してしまうようなこの問いかたには、けれども、もっとも人間の活動に即した根拠がある。それは人間が感知しうる空虚の質にかかわっている。
たとえば、次のような空虚はどうだろうか。「これが過去である。現在は何をしているか」と自問し、「わたくしは何もしていない」と自答して次のようにつづけるのも「なかじきり」においてのことである。
僅かに抒情詩と歴史との部分に遺残してヰタ、ミニマを営んでいる。
わたくしは詩を作り歌を詠む。彼は知人の采録する所となって時々世間に出るが、これは友人某に示すに過ぎない。前にアルシャイスムとして排した詩、今の思想を容るるに足らずとして排した歌を、何故になお作り試みるか。他なし、未だ依るべき新なる形式を得ざる故である。これが抒情詩である。
わたくしは叙述の文を作る。新聞紙のために古人の伝記を草するのも、人の請うがままに碑文を作るのも此に属する。(略)碑文に漢文体を用いるのも、また形式未成の故である。これが歴史である。
と、ここでも「形式未成」をくり返し強調している。
漢詩文体の日記の中に漢詩が混じっている状態、それが鷗外の、いつでもそこから立ちあがり、いつでもそこへ帰ることのできる言葉の基底態であった。その場所を把持したまま、「抒情詩と歴史と」を「ヰタ、ミニマ」として営んでいる、とみずから語った。抒情詩と歴史と――とは鷗外がみずからの中に眺めた店構えである。このことを、もう少し突き詰めて考察してみたいと私は思ってきた。
そのとき、晩年のあのそっけない「委蛇録」が、やはり眼前にあらわれてくる。あの漢詩文体の日記には、もはや漢詩は混じってはいない。それほどにも、最小限に切り詰められているのであった。その代り、全体で詩のように、眺められなくはない。すなわち、あの日記は、詩と日付とが、あるいは抒情詩と歴史とがひとつになった「ヰタ、ミニマ」として、幻覚されてしまうのである。それはいまもまだ、「形式未成」であるからだろうか。