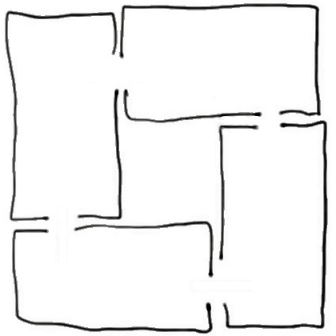過渡期にあらわれる古代的なもの、というとき、それは形式やジャンルの渾沌ということで説明を付けやすい。けれどもここには分りやすい逆説が、ということは陥りやすい逆説がある。
たとえば鷗外がふれている「形式未成」のことを、これから形式が生れる前夜のことだと読むのならば、大いに間違うことになる。鷗外は、形式は生れまい、といっている。それが大正期の、いわゆる鷗外一流の諦めであるが、それ以上でもある。
形式やジャンルが渾沌としているとき、既成の形式やジャンルを「横断」したり、「混淆」したり、「総合」したりする試みがそこここに起るのは自然なことだろう。ところが、それが結果するところは、既成の形式やジャンルにまつわる差異の意識を、観念を、事前よりいっそう強化し、固定化するということに陥りやすい。少し注意すれば、鷗外の「形式未成」という口吻には、既成の形式概念の永続性を無視するという意図のほうがこめられていることに気づかれるだろう。
受け入れる風はしているが、いまある枠を認めてはいない。試みが漢詩、新体詩、短歌、俳句、訳詩にわたったのは、それぞれの領分において力を示したかったためではない。さまざまな領分にふれる動きが、形式生成へのおのずからな動き、来るべき言語を求める自発性の動きであるからにすぎない。たとえ、ついにはそれを諦めるものであっても。
友人某に示すばかり、というとき、そこには自らに恃むこころが潜んでいる。とともに、同時代の読者への諦めと日本語の転変への諦めが明らかである。
子規がもし生きていたら、と思わずにはいられない。玉城徹の指摘したように、子規は俳句にも短歌にも、過大なものを担わせようとしたのではなかった。むしろ「別に一体」を考えたのである。
歌、発句共に永久のものに非ズ、殊に発句は明治に尽くべきものと小生の予言也。詩ハ永久なれども日本文学トハ言ひ難き所あり 若シ永久のものを求めなバ別に一体を創するにあり。これも評論ハ御面会の上ならでハ申がたし。
高浜清(虚子)に宛てた明治二十四年十二月一日の手紙を、『子規全集』から見出して、玉城徹は次のように書いた。
正直に言えば、わたしなども、何度も、この「別に一体」について考えこんだか判らないのである。どうも、うまく行かない。そこで、いわゆる済し崩し論がでてくる。すなわち、その時その時に応じて、当世風のよそおいに変えてゆけば、それで生き延びてゆくことが可能だと言うのである。これは、子規の考えた<改良>とは、根本的に別のものである。
玉城氏は『子規―活動する精神』という本において、このように述べる。おそらくは現代の短歌にもあてられたものであり、それは現代の俳句にも、同じくあてられるものだろう。私が読むとき、それは現代の詩にもあてられると読む。
興味深いのはこの本の中で、子規にロマン主義的精神の発動を見てとっていることである。自殺することになる従弟、藤野古白のロマン主義を指して、「狂を自覚するの狂」と子規は書いた。そこにはおのずから、ロマン主義の発露を掬いとりながら、それを冷却する目が働いている、というように玉城氏は論じてゆく。
ロマン主義とその冷却水との関係は、ヨーロッパ文明を見据えた鷗外においても働いたものである。その振幅は短歌においてみるだけでも、たとえば「我百首」と「奈良五十首」とのあいだに確かめられる。
明治二十八年五月四日から十日まで、遼東半島金州において、第二軍兵站軍医部長の鷗外は、従軍記者正岡子規の訪問を毎日のように受け、俳諧のことを談じ、連句をなした。子規が帰りの船で決定的に身体を病む直前のことである。のちに、「戦争へ行って正岡君と懇意になったのは非常な仕合わせであった」と、鷗外の口から、柳田國男は聞いた。
二人の交流は帰国後数年、浅いものがつづくのみだったが、詩歌の熱を求めつつそれを冷却する二つの精神には深く通うものがあった。子規庵の庭には、鷗外の送ってきた幾袋かの草花の種が蒔かれたこともある。
鷗外のいう「アルシャイズム」を考えるとき私は、どうかするとそれが、この草花の種の袋のように見えることがある。子規にあっても同様に、古代と未来をひとつにした詩歌の徴として確かめられていたものという意味である。