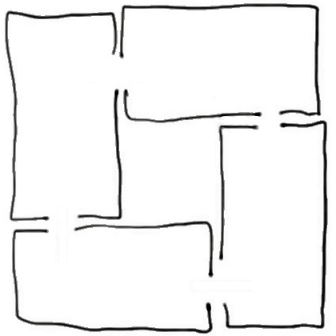玉城氏の子規像にあらわれたロマン主義の説には、実作者の目の働きはもちろん、近代日本文学史の俗説を端から相手にしていないところ、むしろ芸術哲学史の概念を用いて論じるところが面白く、その批評的冷却水の清らかさは、子規に読ませたいと思わせるものである。
玉城氏に促されたかのようにして、私は『ノヴァーリス全集』を読み返す。そうして、ノヴァーリスがゲーテについて対決的に語っているところに出くわす。
古典古代と古代との関係は、「芸術的自然」と自然との関係に類同的である。ノヴァーリスがゲーテに向ける鋭い異議、それは「芸術的自然」というものが様式となることについてである。するとそれは、まるで子規が芭蕉について難じているところのように読める。または、江戸俳諧を一身に受け止めながら、それを脱ぎ捨てていくところにも見える。
肝心なのは、芸術家が古典古代という時代を考察するような仕方で、自然を考察できるかどうかということである――というのも、自然とは生きた古代でなくてなんであろう。自然と自然理解は、古代と古代についての認識同様、時を同じくして生まれる。というのも、古代というものが現に存在していると思うのは、たいへんな間違いだからである。古代はいまはじめて生まれてくる。芸術家の目と魂に見守られて生まれてくるのだ。
「古典古代」の「芸術的自然」は、生れつつあるロマン主義にとっては、「生きた古代」の奔出により破られなければならない緞帳のようなものである。
ベンヤミンが一九一九年に書いた「ドイツロマン主義における芸術批評の概念」という博士論文は、ベルン大学によって教授資格申請を拒まれたときのものとして知られるが、そこでベンヤミンは、散文をポエジーの理念とする考えが、ロマン主義の全芸術哲学を規定している、と書く。ことにシュレーゲルやノヴァーリスにおいて見出された最終的な規定として、ポエジーの理念は散文であり、ポエジーとはもろもろの芸術のなかにまじって存在する散文である、とされることに鋭い注意を向けている。
この長大な論文においてベンヤミンは、やがて彼自身のそれとかさなるようになる詩学を突き止めていることになる。初期ロマン主義は、小説や批評をふくむ散文に、詩を越える可能態としての詩を見出した。彼らのいう小説や批評は、その高次の詩としての核心を、醒めきった散文的形姿の中に根付かせる。批評を作品より高いものとみなしうるという逆説も、ここ、詩の理念を散文とするところから来る。
もし無闇なアナロジーが許されるならば、ノヴァーリスの口をかりて、可能態としての鷗外、批評言語としての子規、といってもよいのである。たとえば、子規とベンヤミンは本質的に通うところがある。断章形式を選んだところ、収集と分類に熱をあげたところ、ジャンルの畑をかまわず横切り、道のないところに道を見出したところ、言語と絵画の相互浸透に惹かれたところ、手当り次第に神話を剥奪していくところ、ほんとうに遊歩を好んだところ、などである。その詩学はともに、現実感覚によって冷却され、距離の計測を怠らない。
子規も鷗外も、散文を基盤とすることによって詩形の太古と未来を示した人たちである。俳人でも歌人でもありえたが、なにより散文による詩人批評家である。歩行の尽きたところから、詩人のような散文家子規は、病床六尺の宇宙を歩いた。その目の前に届けられ、仰臥したまま写生されようとしている草花は、彼にとっての「生きる古代」であった。
ノヴァーリスは、すべては種子である、といった。「形式未成」もまた、生きる古代を目の前にしての呟きである。