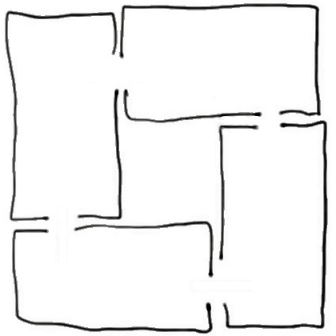エミリー・ディキンソンの家
↓
不死、あるいは回帰する生[全文]より冒頭
ディキンソン、ブランショ
三松幸雄
死を生きること。生きながら死ぬこと。
この生が決定的に途絶え、生きる可能性が永遠に失われるであろう瞬間を知ること。
明らかに、誰もそのような経験をなしえず、それがどのような出来事であるのかを知ることも、証言することもできないだろう。
いま、私は死んでいる、ということ──それは端的に不可能な経験であるように思われる。
しかし、エミリー・ディキンソンあるいはモーリス・ブランショという名の記された作品たちを、互いに近くあらしめ、同時にかぎりなく遠ざけているであろうトポス─二者のあいだを分かつ隔たりにして、双方を関係づけるであろう空虚な場──それは、まさにこの生における死の経験に、ほとんど死そのものを生きることにかかわっているように思われるのだ。
両者のコーパスは、互いに異質な歴史的文脈の内に織り込まれているとはいえ、そこには不協和な倍音をともないつつも互いに共鳴しあういくつかのモティーフがたしかにある。〈生〉と〈死〉の周辺で執拗に持続する彼らの文学的な記入の実践は、おそらく、まさにそのような関係を二者のあいだに開くものとなっているに違いない。
だが、〈生/死〉という対をなす2つの出来事のそれぞれにかけられた問いの負荷は、双方の文学的な歩みのずれに応じた非対称的な偏倚を示してもいる。
たとえば、不死であること、Immortality あるいは不滅。可死(mortal)であることを否定するこの観念が、同時代の文学界からの隠棲者ディキンソンの詩的生涯に横溢する「洪水の主題 Flood subject」であったことは、彼女の書簡に記されたある控えめな証言によって知られている[1]。これに対し、公論界で文筆を揮ったブランショの言語空間を、その初期の時代からくまなく浸していたのは、死(mort)という事象であり、とりわけ、私たちの生の限界に場をもつであろう死ぬこと(mourir)の経験、そのものとしては不可能な経験としての死にゆくことをめぐる終わりなき省察である[2]。
死と不死。これらの観念が二人の文学のあいだで「同一」の事柄を意味しているのでないのは確かであろう。だが、それらの単純な論理的外見が示している「差異」とは異なる次元で、そして二人の──厳密に言えば、「作家」から切り離され、2つの「名」が記された[3]──「作品」群を介して、死と不死のあいだに、〈同一性/差異〉という対立を迂回する別の線が記入されていくように思われる。
彼らの文学において、死と不死はつねに互いに排他的な関係に置かれているわけではない。不死とは、死に対する否定を含意してはいるが、いわゆる宗教的なものへの懐疑を経ずに信憑されるたぐいの「永遠の生」と同一の事柄ではない。とはいえ、テクストのある局面で、不死性の観念がいわば問うに値する事柄として書き込まれていくとき、そこに「宗教」以後の宗教性──宗教なき宗教性──とでも言うべき音域や語調が生じうることは否定できないだろう。神的なものの記憶を断片的にではあれ遺贈する現代の無神論的な探究において、「生き延び」(死後の生 survie; Überleben)の次元がテクスト – 出来事のア・プリオリな構造として捉えなおされるように[4]、不死性の理念は、おそらく、自らの生を書くこと(アウトス・ビオス・グラフエン)──自己に先立つ生の〈自 – 伝 auto-bio-graphia〉──から分離しえない実践としての文学的な虚構そのものが、まさに自らの生と死をめぐって真なるものを証言しようと試みる際に不可欠の観念となるように思われる。
ディキンソンそして/あるいはブランショの文学もまた、互いに異なる経路を通って、〈生- 死〉の過程と不死性の観念が混じりあうトポスに歩みを進めていく。そしてその歩みから、ときに、生の終わりにあって死にゆくとき、ひとは再び誕生し、新たに生きはじめる──したがって、再び死にゆく──そうして同じひとつの生と死が永遠に回帰するという、有限の生と思考の原理にとって根本的に相反するであろう経験が書き継がれていく。そこでは、生から死にいたる不可逆な運命と見えるものが、それらの─同一性と差異を迂回する〈同じもの(ル・メーム) le même〉の──絶えざる中断と再開によって他方へと可逆的に回帰し、かくして誕生と消滅の律動を非連続に刻みながら、自らを永遠に繰り返していくのである。
私の生は終わる前に二度終わった。
それでも私にはまだ残されている
不死が明かしてくれるであろう
三度目の出来事にまみえることが、
とても大きく、絶望的なほど捉えがたい
二度降りかかってきたそれらのように。 [F 1773 / J 1732, undated]死者たちは死につつある者としてよみがえってきた。
[AO 56=191]死にゆくこと、ささやかな、過ぎ去ったもの、
けれども生きていること、これが内に含むのは
幾重にも折り畳まれた死にゆくこと ─
死してあることの休息なしに ─ [F 1023 / J 1013, c. 1865]反復される死の唯一の一撃。死が一度しか起こらないとしても、それは死ぬことが、その本質的な未完了態を、完了しえぬものの完了態を通じて、終わることなく再開し、その反復が数えられないという仕方で、自らを反復するからである〔…〕
[PA 133]